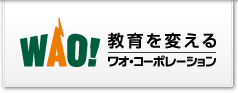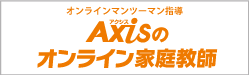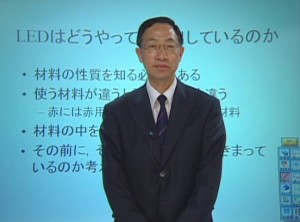科学部探訪
科学は誰にとっても楽しいもの!
宇都宮短期大学附属高校理科部
全国の科学部を訪問し、ユニークな活動を紹介する「科学部探訪」。今回は、栃木県宇都宮市にある宇都宮短期大学附属高校理科部です。大学進学はもちろん、音楽や調理、ファッションの世界を目指す生徒も多いこの学校。理科部のメンバーも、部活動を通して幅広く興味のあることに取り組んでいます。文系進学を目指す人たちもまじる彼らの活動からは、「誰にとっても科学は楽しい」が伝わってきます。
フロントランナー
若返りの方法がここから見つかる!?
不老不死の生物・べニクラゲがもつ驚異の力
京都大学フィールド科学教育研究センター
准教授 久保田 信
人類の永遠のテーマとされる「不老不死」。世界中に不老不死伝説が存在しますが、科学技術が進んだ現在でも、その夢は実現できていません。単細胞生物は分裂によって増えていくので、不老不死の存在といえますが、私たち人間を含む多細胞生物は性を獲得して以降、自分とまったく同じ遺伝子を残すことはできなくなりました。ところが、クラゲの仲間に、その例外がいることがわかった――。驚異の能力をもつ、その生物はどんな生態をしているのか、不老不死のクラゲの研究はどのような未来を私たちにもたらすのか。京都大学の久保田先生の研究をから見えてくるものは……。
「超教養講座」アーカイブ
発光ダイオード(LED)を人工太陽に~北国の環境を考えた光技術の応用
千歳科学技術大学総合光科学部 教授 吉田淳一
1年のうち半分近くが雪に覆われる北海道。農業“大国”ではあるが、自然との闘いを宿命づけられている。なかでも、問題が日照時間。千歳科学技術大学の吉田先生は、LEDを光合成光源とすることで、この問題に挑もうとしている。地理的環境と地球環境保護の観点に立った「バイオフォトニクス」という分野の先駆者! サラダなどに使われる野菜「ルッコラ」の生育に対し、LEDでは通常の太陽光線下に比べてビタミンC含有量が大幅に増えた研究を中心にお話いただきました。
フロントランナー
ウインクだけで操作可能な車椅子を開発
生体信号処理技術で未来を切り拓く
慶應義塾大学理工学部 准教授 満倉 靖恵
「信号」と聞いて、みんなは何を想像するでしょう。道路にある信号? 普通はそうですが、慶應義塾大学の満倉先生が研究対象とする信号は、それとは少し意味合いが異なります。実は、私たちの周りには信号や信号の処理技術があふれている。たとえばリモコンを使ってテレビのチャンネルを変えるのも信号処理です。スマホのアプリを動かすのも同様。さらに、私たちの身体の中には微小ではあるが電気が流れていて、それらは生体信号と呼ばれています。満倉先生はその信号の技術を活かした画期的なシステムを次々と開発、それらはいま社会のさまざまな場面で活用されようとしています。
フロントランナー
暮らしを守り、未来の社会と地球を救う
環境に優しいバイオマスプラスチックス
大阪大学工学部 教授 宇山 浩
プラスチックは、私たちの生活に欠くことのできない素材といって間違いないでしょう。しかし、その大事な素材がいま危機にさらされていることをご存じでしょうか? プラスチックは石油から作られます。そして、石油の量は無限ではありません。それほど遠くない将来に、私のまわりからプラスチックが姿を消すかもしれない・・・・・・。大阪大学の宇山先生は、石油以外のものからプラスチックを作り出す研究の第一人者です。バイオマスをキーワードに、新しいプラスチックの開発に取り組んでいます。地球温暖化など私たちの将来にも大きくかかわってくる、バイオマスプラスチック研究の最前線を見ていきましょう。